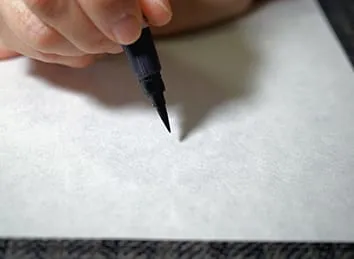
身内に不幸があった際に、近しい方々や勤め先、取引先の会社から弔電(お悔みの電報)をいただいた場合は、後日お礼をするのがマナーです。お礼をするタイミングやお礼の形式など、どのように対応すればよいのかについて、お礼の文例と併せご紹介いたします。
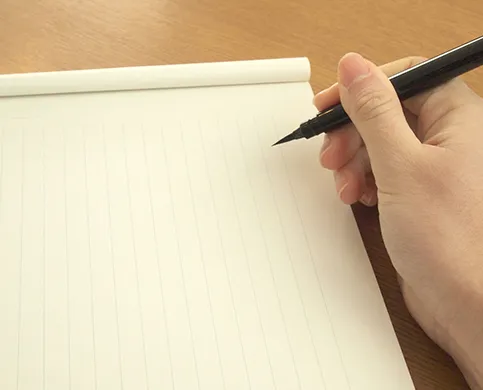
弔電をいただいた際には、後日ハガキか手紙で「お礼状」をお送りするのが基本的なマナーです。
正式には、弔電を送っていただいたお相手方に直接出向いて、ご挨拶することが礼儀とされています。しかし近年では、略儀としてお礼状をお送りするのが一般的となっています。
拝啓
このたびは故〇〇儀の葬儀に際し ご多忙中にもかかわらずご丁寧な弔電を賜り 心より御礼申し上げます
おかげさまで滞りなく葬儀を執り行うことができました
亡き〇〇に代わり 生前の格別のご厚情に深く感謝申し上げます 今後とも、故人同様のご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます
本来ならば 直接参上して御礼を申し上げるべきところですが 略儀ながら書中を持ちまして御礼申し上げます
敬具
令和◯◯年◯月◯日
〒◯◯◯-◯◯◯◯(住所)
喪主 ◯◯◯◯
外 親族一同
謹啓
貴社におかれましてはますますご清祥のことと存じます
このたびは亡き〇〇儀の葬儀に際し ご丁寧な弔電を賜り、誠にありがとうございました
おかげさまでつつがなく葬儀が済みましたことをご報告いたします
略儀ながら、書中にて御礼申し上げます
謹白
令和◯◯年◯月◯日
〒◯◯◯-◯◯◯◯(住所)
喪主 ◯◯◯◯
謹啓
このたびは遠方より温かいお心遣いを賜り 誠にありがとうございました。
ご丁寧な弔電を頂戴し、遺族一同、深く感謝申し上げます
おかげさまで葬儀も無事に済ませることができ、故人も安らかに眠っていることと存じます
なかなかお目にかかる機会も少ない中 このようにご厚情を賜りましたこと 改めて感謝申し上げます
またお会いできる日を楽しみにしておりますが、まずは書中をもちまして御礼申し上げます。
謹白
令和〇年〇月〇日
喪主 〇〇〇〇
弔電のお礼状では、まず「謹啓」「拝啓」などの頭語を記してから、弔電を送ってくれたことへのお礼の言葉を述べます。文頭で時候の挨拶は必要ありません。
そして滞りなく葬儀が終わったことを報告してから、直接のご挨拶ではなくお礼状による略儀となったことのお詫びをしたためます。
最後に結語(謹白、敬具など)で締め、日付、住所、差出人を記して完成です。差出人は「喪主」を記すのが一般的ですが、喪主以外の血縁者を記載する場合は「外 親族一同」などと書きます。
弔電のお礼状は、白やグレーのハガキ、もしくは白無地の手紙を使い、縦書きにでしたためましょう。手紙の場合は封筒も必要となりますが、封筒も事務的な印象のある茶封筒は避け、白無地でフォーマルな一重の和封筒を使うのが一般的です。
また近年はパソコンによるお礼状作成も増えてきましたが、できれば筆や筆ペン、万年筆を使った手書きが望ましいです。お相手との関係性にもよりますが、手書きの方がより心を込めたお礼状となります。またボールペンはなるべく避ける方が良いとされています。
文面では、「終わる」「絶える」「別れる」といった「忌み言葉」や、「たびたび」「しばしば」「いろいろ」などの「重ね言葉」も避けましょう。さらに「(人間関係の)区切り、終わり」を連想させるということから、句読点を使わないのもマナーとされています。
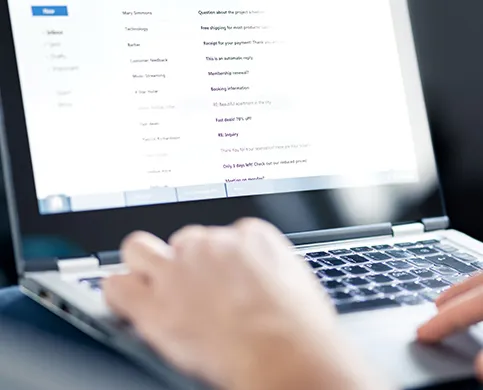
弔電のお礼状はハガキか手紙で送るのがマナーとされており、メールは基本的に避けるのがいいとされています。
しかしお相手との関係性によっては、ハガキや手紙ではなく、メールやお電話でお礼を伝えるというケースもあります。例えば会社の取引先など、普段からメールでのやり取りが一般的な場合は、メールでお礼状を送るケースも見受けられます。しかしメールの場合はお相手に失礼にならないよう、十分に配慮する必要があります。
また、親しい間柄の場合は、お礼状の代わりにお電話で直接お礼の言葉を伝えるケースもありますし、会社の同僚の場合は、お礼状ではなく直接お礼を伝えることも可能です。
直接お会いすることが難しく、「メールやお電話だと礼を失するかもしれない」と少しでも不安を感じるならば、ハガキ、もしくは手紙の形式でお礼状を送るのが良いでしょう。
弔電のお礼状を送るタイミングは、厳密には決まっていません。しかし、葬儀から一週間以内にお礼状を送るのが一般的となっています。弔電を送ってくれた方に、葬儀が滞りなく終わったことを伝える意味でも、葬儀後にできるだけ早くお礼をするのが望ましいのです。
しかし、葬儀後は様々な手続きなどもあり心身共に疲弊してしまうことが少なくありません。大切な人を失ったショックもあり、一週間以内にお礼をすることが難しい場合ことも。
そのような場合は、弔電へのお礼が遅れてしまったことへのお詫びを添えて、お礼状を送るようにしましょう。
弔電のお礼をする際は、基本的にお礼の品物を用意する必要はありません。弔電のみを送っていただいた方にお礼の品を贈ると、かえってお相手に気を遣わせてしまう可能性があります。
ただ、弔電と一緒に香典や供花、供物などをいただいた場合は、その半値ほどの品物を、四十九日が明けた忌明けに「香典返し」としてお返しするのがマナーとなっています。香典返しが必要な場合は、香典返しとともにお礼状を送るのが一般的です。
最近ではプリザーブドフラワーや線香などとセットになった弔電台紙を送られることが増えています。
このような弔電台紙をいただいた場合、基本的にお礼の品物を用意しなくともマナー違反とはならず、お礼状のみで問題ありません。ただ、プリザーブドフラワーや線香を「お供え物」と考え、その返礼として品物を送っても問題ありません。
お礼の品物は香典返しと同じく、石鹸やタオル、緑茶やキャンディなど、いわゆる「消えもの」が一般的です。
弔電を受け取った際には、その心遣いに対する感謝の気持ちをお礼状でお伝えしましょう。また親しい方や会社の同僚、取引先の会社などで不幸があった際に、葬儀・法要への出席が難しい場合は、弔電を使ってお悔みの気持ちをお伝えしましょう。
KDDIグループの電報サービス「でんぽっぽ」では、線香やプリザーブドフラワーとセットになった弔電を数多く取り揃えております。
当日14時までのお申込みなら最短当日でのお届けが可能な商品を豊富に揃えていますので、急な準備の際にも安心です。
弔電をご用命の際は、ぜひ「でんぽっぽ」の電報サービスをご利用ください。